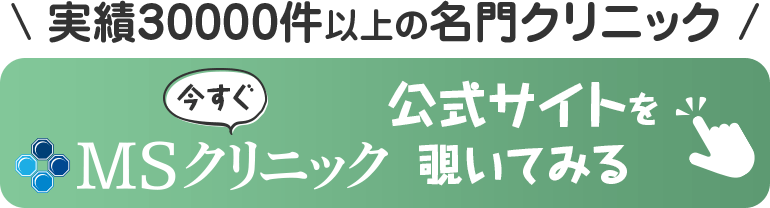「NMNはどれくらい摂取すれば効果あるの?」や「NMNの過剰摂取が心配」という人は多いと思います。
美容や若返りに効果があるとされているNMNですが、その摂取量や摂取のタイミング、そして摂取頻度については様々な情報があるため混乱しやすいかもしれません。
そこでこの記事では、NMNの摂取量や摂取頻度、さらには摂取方法などについて、NMN療法に詳しい医師がわかりやすく解説します。
この記事の目次
NMNとは
NMNとは「ニコチンアミドモノヌクレオチド(Nicotinamide mononucleotide)」と呼ばれる、ビタミンB群の中に含まれる成分のひとつです。
NMNは体内でNAD(nicotinamide adenine dinucleotide)に変わり、このNADが様々な生理活性を示します。
NMNやNADは人間の体内に存在していますが、加齢と共に減少していきます。昨今の研究によって、NMNやNADが不足することで代謝機能や骨密度、さらには眼機能の低下といった老化現象が起きることがわかっています。
さらに、NMNやNADを摂取することで老化現象の改善および予防効果が得られることも判明し、抗老化作用が期待されるとして注目を集めています。
ここで、NADが補充できればNMNは不要の様に思われますが、脳には血液脳関門と呼ばれる血液から脳への物質の動きをコントロルしているゲートがあります。ここを通過しないと脳細胞に物質は届きません。NMNは血液脳関門を通過できますが、NADは血液脳関門を通過できません。また、NADはゆっくり点滴しないと脈が速くなって胸が苦しくなるなどの使い勝手の問題もあるため、NMNを補充するのが一般的になっています。
NMNは特定の食品にも含まれているものの、食品を通じて理想的な摂取量を確保するのは難しく、その代わりとして「NMN点滴」や「NMNサプリメント」が用いられています。
NMNの効果

NMNを摂取することで効果が得られる主な症状として以下のようなことが挙げられます。
- 認知機能の低下
- 視力低下
- 聴力低下
- 運動機能障害
- 心血管疾患
- 脂肪肝
- 免疫機能低下
- 糖尿病
- 腎機能障害
- 不妊
- 肥満
- 炎症
- 睡眠障害 など
いずれも加齢と共に生じやすい症状であることが特徴です。しかし、NADやNMNを摂取することでこれらの症状が改善または予防できる効果があるとされています。
NMNの摂取量
NMNの摂取量について「1日あたりの推奨摂取量」と「最大摂取量」にわけて解説します。
1日あたりの推奨摂取量
NMNの1日あたりの推奨摂取量は150mgから300mgとされています。この理由として、東京大学や慶応義塾大学が実施したヒトを対象にした実験において、1日あたりの摂取量を100mgから250mgに設定しており、なおかつこの摂取量で安全性や筋力改善といった成果が得られたことが挙げられます。
これまでのところ、NMNの1日あたりの摂取量については画一的な規定量こそないものの、ヒトを対象にした研究で用いられた「150mgから300mg」が目安として使われています。
また、NMNは多く摂取するほど有益な結果が得られるものではないとされており、1日あたりの推奨摂取量は150mgから300mgが妥当とされています。
NMNの最大摂取量
NMNの最大摂取量は、1日あたり成人男性で300mgから350mg、成人女性の場合は250mgが上限とされています。
この理由として、厚生労働省が公開している「日本人の食事摂取基準(2020版)」において、NMNが該当する「ナイアシン(NMNはナイアシンの一種)」の耐用上限量が上記のように示されていることがあります。
同じ資料のなかで、ナイアシンを大量摂取した場合、消化器系や肝臓に障害が生じる例について触れられていることから、NMNには目安とされる摂取上限があることを合わせて覚えておきましょう。
NMNの摂取方法
NMNの摂取量がわかったところで、NMNの摂取方法について解説します。
NMNの摂取方法は主に以下のような方法があります。
- NMN点滴
- NAD点鼻薬
- NMNサプリメント
- 食品
NMN点滴
NMNの摂取方法として「NMN点滴」があります。NMN点滴はNMNが配合された製剤を点滴で摂取する方法です。
一般的な製剤1本に150〜200mgのNMNが含まれており、サプリメントや食品を通じた摂取と比較して摂取効率が高いことが特徴です。
現在では最も効率的なNMNの摂取方法として利用されており、NMN療法を実施している医療機関やクリニックなどで受けられます。
NAD点鼻薬
NADの点鼻薬は、文字通り鼻からNADを摂取するスプレーです。1回のスプレーで約12.5mgのNADを摂取できます。
点鼻薬は点滴とサプリメントの中間と位置付けられることも多いのですが、点鼻薬に特有のメリットがあります。それは、鼻からスプレーすることで嗅神経を通じて脳に直接作用すること。
前述の通り、NMNは血液脳関門を通過できますが、NADは血液脳関門を通過できません。また、NMNが血液脳関門を通過しても実際に生理活性を得るためにはNMNからNADへの変換が必要です。しかし、点鼻薬であればNADが脳に直接作用を及ぼす事ができるため、認知症予防やブレインフォグの改善が期待されています。
NMNサプリメント
NMNの摂取にはサプリメントもあります。NMNサプリメントは、NMNが配合されたサプリメントを1日に1~2回の頻度で摂取する方法で、点滴と比較して利便性やコストの面で優れています。
一方、サプリメントによる摂取の場合、小腸で吸収されたものの一部が肝臓を通過するときに代謝または分解される「肝初回通過効果」が起こるため、摂取効率が低下するデメリットがあります。
NMNサプリメントは酵母発酵法もしくは化学合成による2種類に分けられます。酵母発酵法と化学合成の違いは光学異性体の有無で、化学合成のものは光学異性体と呼ばれる生理活性のないNMNが理論上50%ほど含まれます。
ごく簡単に言うならば、同じNMNサプリであっても酵母発酵法の方が化学合成のものよりも効果が期待できると言えます。
ちなみに、酵母発酵法によるNMNサプリは化学合成のものより費用が割高になることを覚えておくとよいでしょう。
食品
NMNを摂取する方法には食品も挙げられます。具体的には、ブロッコリーやアボカド、枝豆といった食品から摂取可能です。
しかし、NMNを推奨摂取量である250mg程度摂取しようとすると、ブロッコリー4,000房、アボカド600個、枝豆20,000個がそれぞれ必要になるため、現実的な摂取方法とは言えません。
NMNを摂取する頻度とタイミング
NMNを摂取する頻度とタイミングについては以下を目安にしてください。
- NMN点滴:月に1回から2回の頻度
- NMNサプリメント:1日1〜2回の頻度
NMNを摂取するタイミングについては特定の時間帯などはありません。サプリメントは飲み忘れを防止するために、朝食後と夕食後のように定期的な摂取ができるサイクルを作ることをおすすめします。
NMNの摂取に関するよくある質問と回答
NMNの摂取に関するよくある質問を紹介します。
NMNを過剰摂取するとどうなりますか?
基本的には尿で排出されるため、過度な心配は必要ありません。しかし、ナイアシンの過剰摂取は消化器系や肝臓に障害が出る可能性があるため、NMNを摂取する際には過剰摂取にならないように注意した方がよいでしょう。
NMNの危険性はどのようなことですか?
これまでのところ、NMNの危険性は指摘されていません。ただし、過度な摂取を避け、適量を守ることをおすすめします。
点滴とサプリメントの違いは何ですか?
摂取効率(吸収量)、時間、そしてコストが違います。点滴はサプリメントと比較して全身にくまなく行き渡りやすく、NMNを効率的に摂取しやすい利点があります。
一方、点滴はサプリよりも割高で、通院や点滴のための時間がかかります。これらの違いを理解したうえで、あなたに最適な方法を選びましょう。
NMNはどんな食品に含まれていますか?
ブロッコリーやアボカド、枝豆、きゅうり、キャベツ、トマト、マッシュルームなどに含まれています。
ただし、推奨摂取量を確保するためには非常に多くの量が必要になるため、食品による摂取は難しいと言えます。
副作用はありますか?
これまでのところNMNの副作用は確認されていません。推奨摂取量を目安にして摂取する限りは過度な心配は不要です。
NMNはどこで入手できますか?
NMN療法に対応している医療機関やクリニックです。医療機関では市販されていない医療機関専用サプリメント「メトセラ N.M.N. (酵母発酵法)」も入手可能ですので、医師に相談してみましょう。
まとめ
NMNの摂取は男性の場合で1日あたり300mgから350mg、女性は250mgが推奨されています。
NMNを摂取する場合は、医療機関で点滴を受けたり、点鼻薬やサプリメントを出してもらったりするのがおすすめです。
MSクリニックでは「NMN点滴療法」と医療機関専用サプリメントの「メトセラ N.M.N.」の治療法が可能です。
また併用することで治療効果が大幅に高まります。
費用については診察料や処方料は無料、点滴代またはお薬代のみとなっており最適な治療法をご提供いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修医師

総院長、医学博士 葉山芳貴
経歴
- 平成14年
- 聖マリアンナ医科大学 卒業
- 平成20年
- 大阪医科大学 大学院 卒業
- 平成22年
- 大手美容形成外科 院長 就任
- 平成27年
- メンズサポートクリニック開設
- 平成28年
- メンズサポートクリニック新宿 院長就任
- 平成28年
- 医療法人清佑会 理事長 就任
資格
医師免許(医籍登録番号:453182)
保険医登録(保険医登録番号:阪医52752)